ナットク!麻雀初心者講座
点計算
符の計算の高速化
符が加算される条件は、面子(刻子や槓子)、アタマ、待ち、ツモの4つ条件でした。
このうち、アタマ、待ち、ツモに加算される数値は2符です。
連風牌は役が重複してると考えて2符+2符で4符になると覚えてください。
ということであとは刻子や槓子のそれぞれの符の数字を覚えてしまえばいいことになります。
下が刻子と槓子の表です。
1・9・字牌の暗槓は32符とすごい数字です。
よく「1・9・字牌の暗槓は1翻分」とも言われます。
30符2翻も60符1翻も同じ得点ですので、32符の増加は点数にも影響しやすいのです。

表の覚え方ですが、綺麗に倍倍に並んでいるのでどこかひとつを基準に覚えてしまえば覚えやすいと思います。
そこで、
「1・9・字牌の暗刻(アンコ)は8符」
最初はこれだけでいいので覚えてください!
なぜ19字牌の暗刻が重要なのか次で説明しましょう。
符の切り上げについて
符は合計の端数を切り上げて計算します。
このうち基本の符(20符)とメンゼン・ロン(10符)には端数がありませんので切り上げに影響しません。
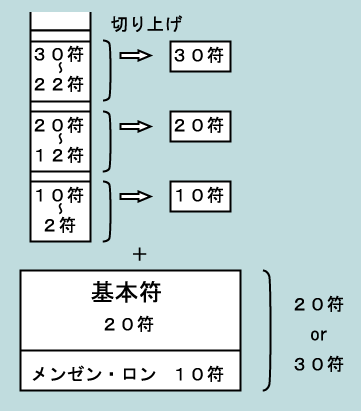
ということは基本符以外(符が加算される4つの条件)を合計させて
12符
22符
32符など
を狙いにいくとうまく切り上げされることになります。
「面子構成(面子とアタマ)」以外は「待ちで2符」、「ツモって2符」、なので0〜4符しか加点されません。
待ちとツモで最大4符つくとすれば
8符以上
18符以上
28符以上など
「面子とアタマ」で取る必要が出てきます。
そこで19字牌の暗刻が一つある場合、 それだけで8符。
うまく切りあがる12符を狙うのにちょうどいい点数なのです。
「19字牌の暗刻(アンコ)は8符」
これを記憶しておけば、19字牌の暗刻ができた瞬間にこれはチャンスだと気付くことができるわけです。
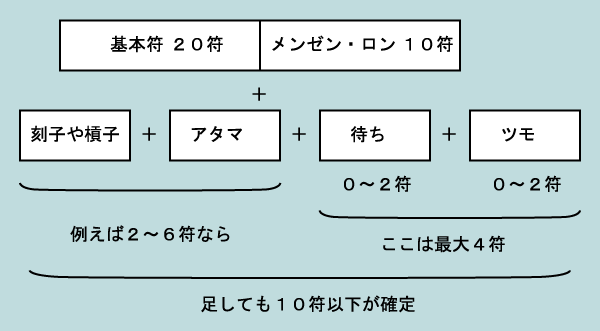
符の計算の省略
前記をさらに応用させると計算の省略ができます。
符を計算する時に、まず面子とアタマの符を合計させます。
刻子・槓子とアタマの符を数えて
2〜6符
12〜16符
22〜26符
32〜36符など
ならばもう符を数える必要がありません。
符の切り上げをおこなって、計算を終了させて構わないのです。
前述したとおり、待ちとツモにつく符は最大で4符。
例えば刻子とアタマで2〜6符だったします。
そこに4符足されたとしても
6〜10符
でどちらにしろ10符に切り上げられるので結果は同じです。
まず刻子・槓子とアタマの符を合計します。
下1桁が0、8の時は、待ちやツモの符を考えます。
下1桁が2〜6なら、符を切り上げて点数を決定します。
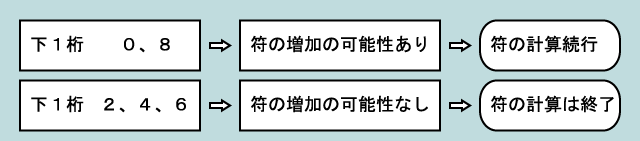
最初に刻子とアタマの符を数えただけで結果が分かってしまう場合もあるのです。
これを利用するとスピーディな計算が行えます。